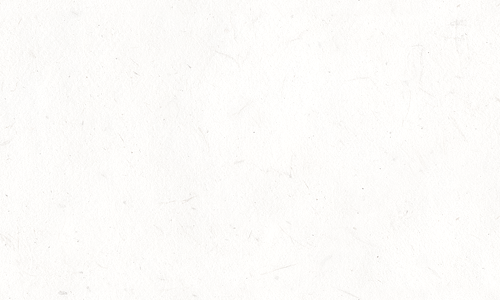下方婚とは?婚活で知っておくべき現実と背景(第1回)

1. 下方婚とは?
「下方婚(かほうこん)」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
これは、結婚相手を選ぶ際に 自分よりも年収や学歴、社会的地位が低い相手と結婚すること を指します。従来の日本社会においては、特に女性が「上方婚(じょうほうこん)」――つまり、自分よりも条件の高い男性を選ぶ傾向が強いとされてきました。しかし近年、社会の変化とともに「下方婚」という現象が注目を集めています。
「上方婚が当たり前」とされてきた背景には、かつての性別役割分担があります。男性が外で働き、女性が家庭を守ることが一般的だった時代には、経済力のある男性と結婚することが安定した生活を送る最適解でした。しかし、今では女性の社会進出が進み、経済的に自立している女性も増加。結果として「収入や地位が低くても、性格や相性を重視して選ぶ」という考え方が広がりつつあります。
2. 下方婚が増えている背景
下方婚が注目されるようになった背景には、以下のような要因があります。
- 女性の高学歴化・高収入化
大学進学率の上昇により、専門職や管理職で活躍する女性が増えています。その結果、結婚市場で「自分より高収入の男性」が減少。相対的に、下方婚を受け入れる女性が増えているのです。 - 価値観の多様化
「お金よりも相性や安心感を大切にしたい」と考える人が増えています。特に再婚市場では、安定感や優しさといった内面的な価値が優先されやすい傾向があります。 - 婚活市場のリアル
国勢調査や婚活データを見ても、年収500万円以上の独身男性は決して多くありません。現実を直視すれば、「理想通りの上方婚」にこだわるほど結婚のチャンスが狭まってしまいます。
3. 男女別の下方婚の受け止め方
下方婚に対する意識は、男女で大きく異なります。
- 女性の場合
「収入や学歴は妥協できるけれど、性格や生活感覚が合うことが大事」と考える女性が増えています。一方で、社会的な視線を気にして「下方婚だと思われたくない」と感じるケースも少なくありません。 - 男性の場合
男性にとって下方婚とは、「自分より高学歴・高収入の女性と結婚すること」を意味します。以前はプライドの問題で敬遠されがちでしたが、今では「共働きで安心できる」「家計を支えてもらえる」と前向きに捉える男性も増加中です。
4. 婚活手段ごとの影響
下方婚をどう捉えるかは、利用する婚活手段によっても違いが見えてきます。
- マッチングアプリ
スペック(年収・学歴・職業)でフィルタリングされやすいため、上方婚志向が強く働きます。ただし「価値観重視アプリ」では下方婚に前向きな出会いも期待できます。 - 婚活パーティー
実際に会って話せるため、プロフィールだけでは見えない魅力が伝わりやすいのが特徴。収入や学歴を超えて「一緒にいて楽しい」と思える人に出会える可能性があります。 - 結婚相談所
データに基づいた紹介が中心ですが、カウンセラーのサポートで「条件にとらわれすぎないマッチング」が可能。特に再婚者や年齢層が高い会員にとって、下方婚は現実的かつ幸せな選択肢となっています。
5. 次回予告
第1回では、下方婚の定義や背景を整理しました。
次回(第2回)では、女性が下方婚を選ぶ場合のメリット・デメリット を深掘りし、「どんな価値観を持つ女性が幸せな結婚につながりやすいのか」を具体例とデータを交えて解説します。
下方婚とは?女性が下方婚を選ぶメリット・デメリット(第2回)

1. 女性にとっての「下方婚」の現実
従来、日本の結婚市場では「女性は男性に経済力を求める」という傾向が強く見られました。特にバブル期以前は「年収・学歴・社会的地位」が結婚相手選びの大きな基準とされ、いわゆる「三高(高学歴・高収入・高身長)」が人気の条件でした。
しかし、時代が変わり、女性の社会進出が進んだ現在では、「必ずしも男性が上である必要はない」という考え方が広がっています。特に30代後半以降の婚活女性や再婚を考える女性にとって、下方婚は現実的かつ前向きな選択肢になりつつあるのです。
2. 女性が下方婚を受け入れるメリット
(1) 結婚のチャンスが広がる
婚活市場で「理想のスペックを満たす男性」を探すのは非常に難しいのが現実です。厚生労働省やIBJのデータによれば、年収600万円以上の独身男性は全体のごく一部。条件を緩和することで出会いの母数が増え、成婚の可能性が高まります。
(2) 性格や相性を重視できる
収入や地位にこだわりすぎると、人柄や価値観の相性を見落としがちです。下方婚を受け入れることで、「一緒にいて落ち着く」「考え方が合う」といった本質的な部分に目を向けられるようになります。
(3) 主導権を持ちやすい
女性の方が収入や学歴で上回る場合、家庭内での意思決定においてリーダーシップを発揮しやすい側面もあります。キャリアを継続したい女性にとっては、自分の仕事を尊重してくれるパートナーを得られる可能性が高まります。
3. 女性にとってのデメリット・不安
(1) 世間体や周囲の評価
「旦那さんは何をしているの?」という会話の中で、無意識に比較されることがあります。自分の方が年収や学歴が高いと知れたとき、親世代から「大丈夫なの?」と心配されることも少なくありません。
(2) 夫婦関係におけるバランス
男性側が「自分の方が下」ということにコンプレックスを抱く場合、喧嘩や意見の食い違いの際にプライドが刺激されやすくなるリスクも。女性側にも「私の方が稼いでいるのに…」という意識が芽生え、対等な関係が崩れる危険性があります。
(3) 将来的な経済的不安
共働きが前提であれば問題ありませんが、出産や育児などで一時的に仕事をセーブする際には「夫の収入だけでは不安」という状況に直面する可能性もあります。長期的な家計プランニングが重要になります。
4. 婚活手段別に見る「女性と下方婚」
(1) マッチングアプリ
アプリでは「年収○万円以上」「大卒以上」といった条件検索が主流。そのため、女性が自ら条件を緩めなければ下方婚の可能性は低め。ただし、プロフィールや写真の印象よりも「会話の気楽さ」を重視する女性が、結果的に下方婚の相手を選ぶケースもあります。
(2) 婚活パーティー
直接会って話せるため、収入や職業の差よりも「気が合う」「優しい」といった印象が残りやすいのが特徴です。条件を重視して参加する女性も多いですが、実際に会って話してみたら「この人がいい」と思えるケースは少なくありません。
(3) 結婚相談所
カウンセラーが介在することで、「年収や学歴にとらわれないマッチング」が可能。特にフォリパートナーのように相性や価値観に基づいたサポートを重視する相談所では、下方婚による幸せな成婚が数多く実現しています。
5. 女性が下方婚で幸せになるためのポイント
- 自分が何を重視したいか(経済力?安心感?家庭観?)を整理する
- 世間体ではなく「二人の生活の満足度」を基準にする
- 長期的なライフプランを話し合い、共働き・子育ての分担を具体的に考えておく
- 下方婚を選ぶ場合でも「尊敬できる部分」を見つけて結婚する
まとめ
女性にとって下方婚は「妥協」ではなく、「現実的かつ幸せをつかむための柔軟な選択肢」です。条件を緩めることで、これまで出会えなかった相手とつながり、人生を共にできる可能性が広がります。
次回(第3回)は、男性が下方婚を選ぶ場合の心理と実態について掘り下げます。
下方婚とは?男性が下方婚を選ぶ心理とその現実(第3回)

1. 男性にとっての下方婚とは?
「下方婚」という言葉は、一般的に女性が自分よりも収入や学歴の低い男性と結婚する場合をイメージしがちです。しかし、男性側にも下方婚の現実があります。それは、自分より高収入・高学歴の女性と結婚することです。
従来の日本社会では「男性は家計を支える存在」として期待されてきました。そのため「妻が自分より稼ぐ」ことにプライドを刺激される男性も少なくありませんでした。しかし時代は変化し、今では「妻の収入が高い方が安心できる」と感じる男性も増えています。つまり、男性にとっての下方婚は必ずしもネガティブなものではなく、現代的な結婚観の一部と捉えられるようになってきました。
2. 男性が下方婚を受け入れるメリット
(1) 経済的な安心感
共働き世帯が増えるなか、妻の収入が高いことは大きな支えになります。住宅ローンや教育費、老後資金など長期的なライフプランに余裕が生まれ、精神的にも安定しやすくなります。
(2) 自分のキャリアを柔軟に考えられる
「自分が必ず大黒柱でなければならない」というプレッシャーから解放されることで、転職や起業などキャリアの選択肢を広げやすくなります。妻の収入が支えとなり、挑戦できる環境を得られるのは大きな魅力です。
(3) 対等なパートナーシップ
妻が経済的に自立していることで、家事や育児を分担する「対等な夫婦関係」を築きやすくなります。経済面で依存されすぎない分、精神的にも健全な関係を保ちやすいのです。
3. 男性にとってのデメリット・不安
(1) プライドや劣等感
「妻の方が年収が高い」という状況に、無意識のうちに劣等感を抱く男性もいます。特に親世代や職場の同僚からの視線を気にしてしまう場合、ストレスや家庭内トラブルにつながることがあります。
(2) 家庭内のパワーバランス
収入の高い妻が家庭内で主導権を握りやすくなるケースもあります。男性が「自分の意見が通らない」と感じると、夫婦関係に溝が生まれやすくなる点には注意が必要です。
(3) 社会的な偏見
今でこそ「共働きが当たり前」ですが、「男が稼ぐべき」という価値観が根強く残っている地域や世代もあります。そうした場面では肩身の狭さを感じることもあるでしょう。
4. 婚活手段別に見る「男性と下方婚」
(1) マッチングアプリ
プロフィール検索では「女性の年収」を条件に設定する男性は少なく、多くの場合は見た目や趣味の相性が優先されます。そのため、結果的に「相手が自分より高収入」になるケースは多々あります。
(2) 婚活パーティー
実際に会話を通じて惹かれるケースが多いため、年収や学歴の差が障害になりにくいのが特徴です。女性がキャリア志向の場合でも、男性がそれを応援できるならば自然と下方婚の関係が成立します。
(3) 結婚相談所
相談所では、男性が「妻に共働きを希望するか」「専業主婦を希望するか」といった条件を提示することが多いです。そのため、下方婚を受け入れる男性は最初から「共働き前提」で活動する傾向が強く、価値観の合う女性と出会いやすいのが利点です。
5. 男性が下方婚で幸せになるためのポイント
- プライドよりも「二人の生活の安定」を優先する
- 相手のキャリアを尊重し、サポートする意識を持つ
- 家事や育児の分担を前提に話し合い、役割を明確にする
- 「稼ぎ=優劣」ではなく、「相互補完」と考える視点を持つ
まとめ
男性にとっての下方婚は、「恥ずかしいもの」ではなく「新しい夫婦の形」を築くきっかけになり得ます。大切なのは、社会的な価値観よりも二人の関係性をどう作るかという点です。下方婚をポジティブに受け入れることで、安心感と尊重に基づいた結婚生活が実現できます。
次回(第4回)は、「下方婚の成功事例と失敗事例」 を取り上げ、実際にどのようなケースで幸せな結婚につながったのか、逆にトラブルに発展したのかを詳しく解説します。
下方婚とは?成功事例と失敗事例から学ぶリアルな教訓(第4回)

1. 下方婚の現実を知ることの大切さ
下方婚は「条件に妥協する結婚」と誤解されることもありますが、実際には 価値観や相性を優先する柔軟な選択 です。しかし一方で、現実的な課題に直面して「こんなはずじゃなかった」と感じてしまうケースも存在します。ここでは、成功と失敗の両方の事例を紹介し、そこから学べるポイントを整理していきます。
2. 下方婚の成功事例
事例①:年収差を超えた安心感(女性40代・再婚)
40代女性で年収700万円のキャリア女性。相手は年収400万円の男性でした。最初は親や友人から「収入面で不安じゃない?」と言われたそうですが、実際に生活を始めると男性は家事や育児に積極的で、精神的な支えとなったとのこと。結果として「経済力の差は気にならない。むしろ支え合える関係が心地よい」と感じ、幸せな結婚生活を送っています。
学びポイント
- お金の差よりも「家庭を支える意欲」が幸福度に直結する
- 周囲の評価よりも本人たちの安心感を基準に考えることが大切
事例②:男性が妻のキャリアを尊重(男性30代・初婚)
30代男性(年収500万円)が、年収800万円の女性と結婚したケース。結婚後、妻が管理職に昇進しさらに多忙になりましたが、夫は在宅勤務を活かして家事・育児を積極的に分担。「妻の成功は自分の誇り」と語り、周囲からも「理想的な共働き夫婦」と見られています。
学びポイント
- プライドよりも「応援の気持ち」を持てる男性は強い
- 夫婦間で役割を柔軟に変えられることが下方婚の成功要因
事例③:結婚相談所でのマッチング(再婚同士)
結婚相談所を通じて出会ったバツイチ同士のカップル。女性の方が学歴・年収ともに高かったが、相談所カウンセラーのサポートで「条件よりも価値観重視」のマッチングが成立。お互いに「再婚で安心できる相手を探したい」という目的が一致していたため、成婚に至りました。
学びポイント
- 第三者(相談所)の介入があることで、条件に縛られずに出会える
- 再婚者にとっては「下方婚」がむしろ現実的で自然な選択肢
3. 下方婚の失敗事例
事例①:収入差を理由に不満が積み重なる
女性が年収650万円、男性が年収350万円というカップル。結婚当初は「気にしない」と言っていたものの、生活費の負担割合を巡って対立が増加。女性が「なぜ私の方が多く出さなければならないのか」と不満を抱き、男性も「養われているようで辛い」と感じるようになり、最終的に離婚に至りました。
失敗要因
- 金銭的な取り決めを曖昧にしたまま結婚したこと
- 「気にしない」という言葉の裏にある本音を見落としたこと
事例②:親世代の反対
男性が女性よりも学歴・収入が低かったケースで、親から「もっと条件の良い相手を探した方がいい」と言われ続けた結果、女性が精神的に疲弊。本人たちは問題を感じていなかったものの、周囲の反対が原因で破談となりました。
失敗要因
- 親世代の価値観を軽視していた
- 事前に家族との意識調整をしていなかった
事例③:コンプレックスの爆発
女性が男性よりも年収が高い状況で、男性が仕事で落ち込んだ際に「どうせ俺より稼いでるくせに」と口にしてしまった事例。普段は表に出さないものの、劣等感が積もり積もって爆発した瞬間に関係が悪化。夫婦の信頼関係が揺らぎました。
失敗要因
- 劣等感を素直に話し合わずに放置してしまった
- 精神的なバランスを取る工夫が不足していた
4. 成功と失敗の分かれ道
これらの事例から見えてくるのは、下方婚が成功するか失敗するかは 「条件そのもの」ではなく「受け止め方」 に大きく依存しているということです。
- 金銭感覚や生活の分担を事前にしっかり話し合う
- 劣等感や不安をオープンに共有し、早めに解決する
- 周囲(親・友人)の意見を踏まえつつも「二人の軸」を持つ
これらを意識することで、下方婚でも十分に幸せな結婚生活が築けます。
まとめ
下方婚は「失敗リスクが高い」と思われがちですが、成功事例からもわかるように、むしろ相性や価値観を重視する結婚として大きな可能性を秘めています。大切なのは「条件」ではなく「二人の努力」と「受け止め方」です。
次回(第5回)は、「下方婚を前向きに選ぶための考え方と婚活実践法」 を解説します。
下方婚とは?前向きに選ぶための考え方と婚活実践法(第5回)

1. 下方婚は「妥協」ではなく「戦略」
婚活において「条件に妥協するのは嫌」と考える人は少なくありません。しかし、下方婚は単なる妥協ではなく、自分の幸せを広げるための戦略的な選択 です。社会的な条件に縛られず、自分に合うパートナーを見つけるためには、下方婚を「一つの可能性」として受け入れる姿勢が重要です。
2. 下方婚を前向きに考えるための3つの視点
(1) 幸せの基準を「条件」から「日常の満足度」へ
結婚生活は年収や学歴だけで成り立つものではありません。むしろ大切なのは、毎日の生活における安心感や楽しさです。相手の学歴や収入が低くても、「心から信頼できる」「一緒に笑い合える」と感じられる相手なら、結果的に高い幸福度につながります。
(2) 夫婦は「お互いに補い合う関係」である
収入や学歴が一方的に高い・低いことを「優劣」と考えるのではなく、強みを持ち寄って補い合う関係 として捉えましょう。例えば、妻が高収入で夫が家事や子育てに積極的であれば、それは立派な「役割分担」です。上下関係ではなく、相互補完型のパートナーシップを意識することが重要です。
(3) 周囲の目より「二人の価値観」を優先
親や友人から「もっと条件の良い人がいるはず」と言われることもあるでしょう。しかし、結婚生活を送るのは他人ではなく自分自身です。大切なのは「この人と一緒にいたい」と思える気持ちであり、世間体に左右されすぎない軸を持つことが幸せな下方婚につながります。
3. 婚活手段別・下方婚の実践法
(1) マッチングアプリでの工夫
アプリは条件検索が基本のため、どうしても「上方婚志向」が強く出やすい場です。しかし、プロフィールに「価値観重視」「一緒にいて楽しい人を探しています」と書くだけで、条件よりも相性を大切にする人とマッチしやすくなります。
また、相手の職業や年収に囚われず「会ってみてどう感じるか」を重視する姿勢がポイントです。
(2) 婚活パーティーでのアプローチ
婚活パーティーは、実際に会話してフィーリングを確認できる場です。条件を事前に意識しすぎるよりも、「自然に話せた人」「笑顔が素敵だった人」に注目すると、結果的に下方婚に前向きな出会いにつながることがあります。
特に女性は、収入や地位が低めでも「家庭的」「誠実」という魅力を持つ男性に出会いやすい環境です。
(3) 結婚相談所の活用
結婚相談所では、担当カウンセラーが条件だけでなく「性格の相性」「価値観」を重視した紹介をしてくれます。下方婚に対して不安を抱く会員に、現実的なデータや過去の成功事例を示してくれるため、安心して一歩を踏み出せます。
特にフォリパートナーのように「マーケティング的戦略婚活」を実践している相談所では、条件に縛られすぎず、自分に合った出会いを戦略的に作り出せるのが大きな特徴です。
4. 下方婚を幸せにするための具体的な行動
- ライフプランを共有する
収入の差がある場合は、家計の分担や将来設計を早めに話し合う。 - お互いの強みを認め合う
「自分にはできないことを相手が補ってくれている」と感謝する。 - 劣等感を放置しない
プライドや不安は隠さずにオープンに共有する。 - カウンセラーや第三者に相談する
客観的な視点を取り入れることで、不安を軽減できる。
まとめ
下方婚は、条件に妥協するのではなく、相性や価値観を優先した幸せな結婚への道 です。前向きに捉え、実践的に動くことで「自分らしいパートナーシップ」を築けます。
次回(第6回・最終回)は、「下方婚の未来と、結婚相談所フォリパートナーでの実績」 を取り上げ、これからの婚活市場における下方婚の意味を総括します。
下方婚とは?これからの婚活市場とフォリパートナーの実績(第6回・最終回)

1. 下方婚が当たり前になる時代へ
これまで「下方婚は珍しい」「妥協の結婚」と見られがちでしたが、社会の変化に伴い、今後は 自然で一般的な選択肢 になると考えられます。
背景には以下の要因があります。
- 女性の高学歴化・高収入化:男女の経済格差は縮小し、むしろ女性が上回るケースも珍しくない。
- 共働き世帯の増加:2020年代には夫婦の7割以上が共働き世帯。家計は「二人で築く」ものへとシフト。
- 価値観の多様化:結婚の目的が「経済的安定」から「人生のパートナーシップ」へ変化。
こうした社会背景から、今後は「下方婚」という言葉自体が特別視されず、むしろ 幸せな結婚の形の一つ として受け入れられていくでしょう。
2. 下方婚を成功させる世代別のポイント
20代~30代前半
キャリア形成期にあるため、収入や学歴よりも「将来性」や「価値観の一致」を重視すると良い時期。相手が下方婚であっても、一緒に成長できる関係を築くことで大きな可能性が広がります。
30代後半~40代
現実的に結婚を意識しやすい世代。特に女性は「同年代以上で自分より高収入」という条件が難しくなるため、下方婚を選択肢に入れることで出会いが一気に広がります。
再婚希望者
再婚者にとっては「条件よりも安心感や生活感覚の一致」を重視する傾向が強いです。そのため、下方婚はむしろ自然な結婚の形として選ばれやすくなります。
3. 婚活手段と下方婚の未来
マッチングアプリ
AIによる相性診断が進化しており、「条件マッチ」ではなく「価値観マッチ」が主流になる流れがあります。これにより、下方婚が成立するケースが増加する可能性があります。
婚活パーティー
オンラインとオフラインの融合が進み、気軽に出会える場が多様化。条件よりも「話して楽しいかどうか」が重視され、下方婚へのハードルが下がるでしょう。
結婚相談所
特に相談所では「成婚=ゴール」ではなく、「幸せな結婚生活を続けられるか」を意識したサポートが求められています。条件に縛られず、相性を重視する流れが強まる中で、下方婚は重要なキーワードになっていきます。
4. フォリパートナーにおける下方婚の成婚実績
結婚相談所フォリパートナーでは、下方婚による多数の成婚実績 を誇ります。特に注目すべきは以下の点です。
- マーケティング的戦略婚活
会員一人ひとりの強みや魅力を可視化し、相手に伝わる形でアプローチを行うため、「条件で不利」と思われがちなケースでも成婚につながりやすい。 - 具体的な成功例
- 年収差が300万円あっても「価値観が合う」と感じて半年で成婚
- 学歴差が大きいものの「家庭観が一致」して再婚同士で成婚
- 男性が妻より収入が低いケースでも「サポート力」を評価されて幸せな結婚へ
これらの事例は、「下方婚はリスク」ではなく「新しい幸せの形」であることを示しています。
5. まとめ:下方婚の未来を前向きに捉える
下方婚は、かつてはネガティブな意味で使われることもありましたが、現代では 幸せな結婚を実現するための自然な選択肢 です。
- 条件に縛られず、相性や価値観を重視する
- 周囲の目より、自分たちの安心感を優先する
- 第三者(相談所)のサポートを活用して不安を減らす
これらを実践することで、下方婚でも充実した結婚生活が築けます。
👉 そして、実際に多くの下方婚成婚を実現しているのが 結婚相談所フォリパートナー です。
あなたも一歩を踏み出せば、条件に縛られない本当の幸せが見つかるかもしれません。
フォリパートナー編集部