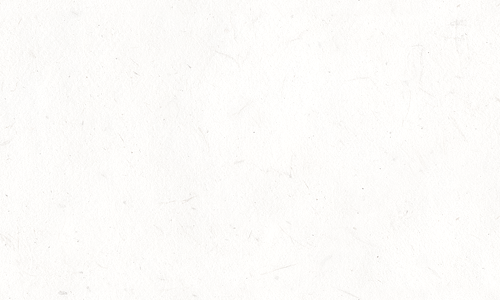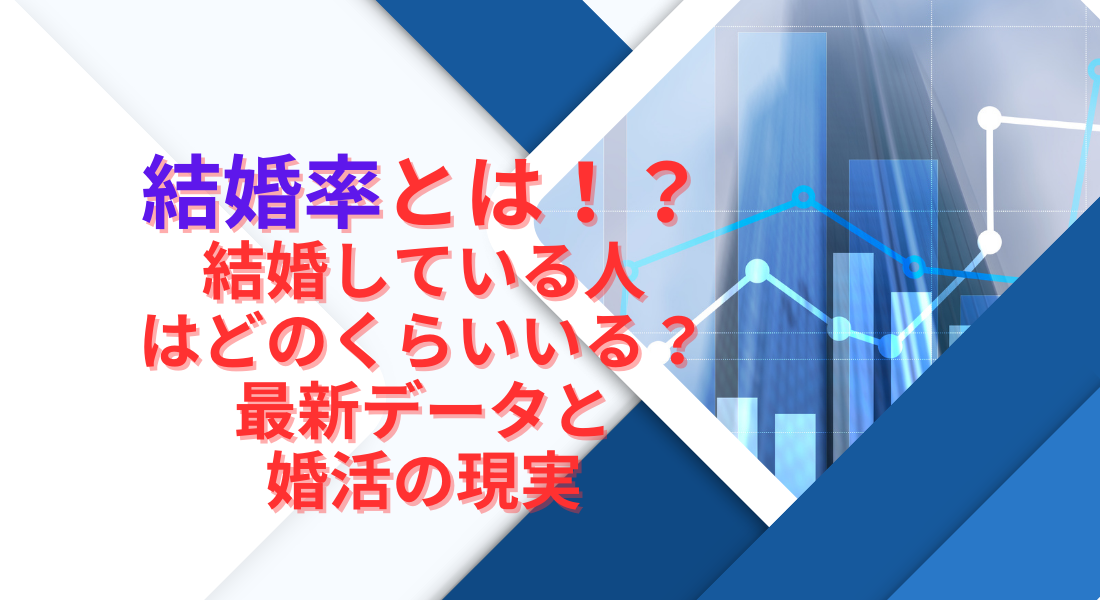
【第1回】結婚している人はどのくらいいるの?最新の結婚率から見る日本のリアル

はじめに:結婚率とは何か?
「結婚率」という言葉を耳にすることは多いですが、実は統計上では複数の意味があります。
代表的なものは以下の2つです。
- 有配偶率(既婚者の割合)
人口に対して「結婚している人がどれくらいいるか」を示す指標。 - 婚姻率(人口1,000人あたりの結婚件数)
年間にどれだけの人が結婚しているかを示す指標。
婚活中の方が気になるのは「今の日本では結婚している人がどのくらいいるのか」「自分は結婚できるのか」という点でしょう。本コラムでは最新データを引用しながら、結婚率の実態を詳しく解説していきます。
1. 日本の結婚率の現状
厚生労働省の「人口動態統計」(引用)によれば、日本の婚姻率(人口1,000人あたりの婚姻件数)は 2023年で約4.0件 と報告されています。
これは1970年代の10件近い数値から比べると半分以下であり、少子化や晩婚化の背景を如実に表しています。
一方、総務省の国勢調査を基にした「有配偶率」を見ると、30代後半で結婚している人の割合は以下のようになります(引用データ)。
- 男性30〜34歳:既婚率約47%
- 男性35〜39歳:既婚率約63%
- 女性30〜34歳:既婚率約62%
- 女性35〜39歳:既婚率約73%
つまり30代後半までには、多くの人が結婚していることが分かります。
2. 年代別にみる結婚率
結婚率は年代ごとに大きく変わります。
- 20代前半(20〜24歳)
男性の既婚率は約5%程度、女性は約10%前後。近年ではほとんどの人が未婚。 - 20代後半(25〜29歳)
男性既婚率は約25%、女性は約40%。「結婚適齢期」と呼ばれる時期ですが、今は未婚者の方が多数派。 - 30代前半(30〜34歳)
男性で約40%、女性で約60%が既婚。男女の結婚率に差が出やすい世代。 - 30代後半(35〜39歳)
男性約63%、女性約73%。結婚している人が多数派になる。 - 40代以降
男女ともに既婚者が7割以上。ただし「生涯未婚率」(50歳時点で一度も結婚していない人の割合)は増加しており、男性は約28%、女性は約18%(2020年国勢調査より引用)。
このデータから、「結婚しない人が増えている」とは言えど、多くの人はいずれ結婚しているという事実も浮かび上がります。
3. 男女別でみる結婚率の違い
男女では結婚のしやすさやタイミングに違いがあります。
男性の場合
- 20代では経済力が安定していないため、結婚率は低め。
- 30代に入ると年収やキャリアが安定し、結婚率が大きく上昇。
- 40代以降も結婚は可能だが、未婚のまま50歳を迎える割合は女性より高い。
女性の場合
- 20代後半から30代前半が結婚率のピーク。
- 年齢が上がると結婚率は鈍化するが、30代後半でも7割近くが既婚。
- 晩婚化が進んでいるとはいえ、男性より早い段階で結婚している傾向が強い。
4. 婚活世代にとっての「結婚率」の意味
婚活をしている方にとって結婚率は「結婚できる可能性」を示す目安になります。
たとえば、30代半ばで結婚している人が6〜7割いるとすれば、「3〜4割は未婚である」ことも同時に意味します。
つまり「結婚できるかどうか」は本人の行動次第。婚活を積極的に始めることで、結婚率を上げる側に入ることができるのです。
まとめ(第1回)
今回の第1回では、結婚率の基本的な意味と年代別・男女別のデータを紹介しました。
- 日本の婚姻率は1970年代から半分以下に低下
- 30代後半までに結婚している人は男性63%、女性73%
- 男女では結婚率の上がるタイミングが異なる
次回(第2回)は、「結婚率が下がっている背景」 を社会的要因(晩婚化、非正規雇用、価値観の多様化など)から詳しく解説します。
【第2回】結婚率が下がっている背景|なぜ結婚する人が減っているのか?

1. 婚姻数の減少という現実
厚生労働省「人口動態統計」(引用)によると、日本の年間婚姻件数は1970年代には 約100万組 でした。ところが2023年には 約48万組 と、半世紀で半分以下にまで落ち込んでいます。
人口減少の影響もありますが、結婚に対する価値観や社会構造の変化が大きな要因となっています。
2. 晩婚化の進行
結婚率が低下している最大の要因のひとつが「晩婚化」です。
- 男性の平均初婚年齢:31歳(2022年 厚労省統計より引用)
- 女性の平均初婚年齢:29.5歳
これは1980年頃と比べると、男女ともに約4歳以上遅くなっています。
晩婚化の背景には以下のような要因があります。
- 進学率の上昇:大学・大学院進学者が増え、社会に出るのが遅くなった。
- キャリア重視:特に女性が仕事を優先し、結婚を後回しにする傾向が強まった。
- ライフスタイルの多様化:「結婚=人生の必須イベント」ではなくなってきた。
3. 非正規雇用と経済的不安
結婚率の低下には「経済的な安定」が大きく関わっています。
国税庁の調査(引用)によると、男性の平均年収は1997年をピークに下がり続けており、特に20代後半〜30代前半男性の所得は伸び悩んでいます。さらに非正規雇用の割合は全労働者の約4割を占めており、安定的な収入を得にくい環境が続いています。
多くの男性が「経済的に結婚できない」と考え、また女性も「安定した生活が見込めないなら結婚に踏み出せない」と感じるケースが増えています。
4. 女性の自立と価値観の変化
かつては「結婚して家庭に入ること」が女性の一般的なライフコースでしたが、今では状況が大きく変わりました。
- 共働き世帯の増加:総務省「労働力調査」によると、2022年の共働き世帯数は約1,200万世帯で、専業主婦世帯(約500万)を大きく上回る。
- キャリア志向の強まり:女性が自立して働くことが一般化し、結婚の必要性が相対的に低下。
- 「自由な生き方」を重視:趣味や仕事を大切にし、結婚に縛られない人生を選ぶ女性が増えている。
このように女性の生き方が多様化したことで、「結婚=必須」ではなく「選択肢のひとつ」へと変わってきました。
5. 恋愛・出会いの変化
さらに結婚率低下の背景には「出会いの形の変化」も関わっています。
- 自然な出会いの減少:地域や職場でのつながりが希薄化。
- マッチングアプリの普及:出会いは増えたものの、「恋愛目的」や「遊び目的」の人も多く、結婚に至らないケースが多い。
- 恋愛離れ:内閣府調査によると、20代男性の約40%、20代女性の約25%が「異性との交際経験なし」と回答(引用データ)。
恋愛や交際が減少すれば、当然ながら結婚率も下がることになります。
6. 結婚に対する心理的ハードル
最後に、心理的な要因も大きいです。
- 「離婚が増えているから不安」
- 「家庭を持つ責任が重すぎる」
- 「一人でも楽しく生きられる」
こうした考え方は特に都市部の若い世代で広がっており、結婚を先延ばしにする理由となっています。
まとめ(第2回)
結婚率が下がっている背景は、単に「結婚しない人が増えた」だけではなく、
晩婚化・経済的不安・価値観の多様化・出会いの減少 が複雑に絡み合っていることが分かります。
次回(第3回)は、「国際比較でみる日本の結婚率」 を取り上げます。他国と比べて日本の結婚率がどのような特徴を持っているのかを解説し、婚活へのヒントを探ります。
【第3回】結婚率の国際比較|日本は本当に結婚しない国なのか?

1. 日本の結婚率は国際的に低い?
「日本人は結婚しなくなった」と言われますが、実際に海外と比べてどうなのでしょうか。
国連やOECDの統計(引用データ)によると、婚姻率(人口1,000人あたりの婚姻件数)は以下のようになっています。
- 日本:4.0(2023年)
- アメリカ:5.0前後
- イギリス:4.3前後
- フランス:3.5前後
- 韓国:3.7(アジア最低水準)
- 中国:6.8(ただし減少傾向が急速)
このデータを見ると、日本の婚姻率は確かに下がっていますが、極端に低いわけではなく、欧州諸国とほぼ同水準 であることが分かります。
2. 欧米諸国との違い:事実婚・同棲の多さ
日本の結婚率が欧米より低く見える理由の一つに、「事実婚や同棲の文化の違い」があります。
- フランスや北欧諸国では、事実婚が一般的で「婚姻届けを出さない同棲カップル」が多数存在。
- 子どもの出生のうち、フランスでは約6割以上が婚外子(事実婚カップルからの出生)といわれています(引用データ)。
- 一方、日本では依然として「結婚=法律婚」が基本であり、同棲や事実婚はまだ少数派。
つまり、数字上は結婚率が同程度でも、実態としては「結婚の形」が国によって大きく異なる のです。
3. アジア諸国との比較
近隣のアジア諸国でも、結婚率は下がっています。
- 韓国:少子化と未婚化が深刻。婚姻率は日本より低く、特に30代の未婚率は男性で50%超。
- 中国:かつては婚姻率が高かったが、都市部を中心に急速に低下。2020年代に入ってからは若者の未婚化が加速している。
- 台湾:日本と似た傾向で、晩婚化が進行。
これらの国々でも「教育・仕事を優先する価値観」や「住宅・経済負担の大きさ」が結婚率を押し下げており、日本と同じ課題を抱えています。
4. 結婚観の違いが生むデータの差
各国の結婚率を比較する際に注意すべき点は、「結婚観」や「家族観」が異なる ということです。
- 日本:法律婚を前提とし、婚姻率=結婚している人の数をほぼ反映。
- 欧米:事実婚・同棲が多く、婚姻率だけでは家庭形成の実態が見えない。
- アジア:親の期待や家族制度が強く影響。婚姻率の低下は社会問題化しやすい。
したがって、「日本の結婚率が低い=結婚していない人が多い」と単純に結論づけるのは誤りです。むしろ、日本では法律婚の比率が高く、結婚した人の割合は依然として多い のが特徴です。
5. 婚活へのヒント
国際比較から分かるのは、結婚率が下がっているのは日本だけではなく、世界的な潮流 だということです。
しかし、欧米では「事実婚」や「同棲」で家庭を築く文化が根付いているため、結婚率が低くても出生率がある程度維持されています。
一方の日本は「結婚してから出産」という流れが強いため、結婚率の低下がそのまま少子化に直結 しています。
つまり婚活市場では、今後も「結婚したい人」と「結婚に積極的でない人」がはっきり分かれる時代になるでしょう。
まとめ(第3回)
- 日本の結婚率は国際的に見ても低いが、欧州諸国と同程度
- 欧米では事実婚・同棲が多く、日本は「法律婚中心」という違いがある
- アジアでも婚姻率は下がっており、日本と同じ課題を抱えている
- 日本では結婚が出産と直結しているため、結婚率の低下は社会的影響が大きい
次回(第4回)は、「結婚率と年収・学歴・地域差の関係」 に焦点を当てます。婚活を進める上で知っておくべきリアルなデータを具体的に解説します。
【第4回】結婚率と年収・学歴・地域差の関係|婚活に役立つリアルデータ

1. 結婚率と年収の関係
結婚率を語る上で避けて通れないのが「経済力」です。
内閣府や国税庁の調査(引用)によれば、年収が高いほど既婚率も高い という相関が明らかになっています。
- 男性年収400万円未満 → 既婚率約30%
- 男性年収400〜600万円 → 既婚率約55%
- 男性年収600〜800万円 → 既婚率約70%
- 男性年収800万円以上 → 既婚率80%超
特に男性においては「安定した収入=結婚できる確率が高い」と言えます。
一方、女性の場合は年収による差は比較的少なく、むしろ「年収が高くても結婚するかどうかは本人の意思による部分が大きい」とされています。
2. 学歴と結婚率の関係
学歴も結婚率に一定の影響を与えています。
- 男性の場合
高学歴ほど結婚率が高い傾向。安定した職業につきやすく、経済力に直結するため。 - 女性の場合
一昔前は「高学歴女性は結婚しにくい」と言われていましたが、現在ではむしろ「高学歴女性ほど婚姻率が高い」というデータも出ています(引用データ)。
理由は、キャリアを積みつつ結婚を望む女性が多く、同じように安定した男性との結婚に至りやすいからです。
つまり、学歴そのものよりも 「職業・年収・価値観」 が結婚率に影響を与えているのです。
3. 地域差と結婚率
結婚率には地域ごとの差も存在します。
- 都市部(東京・大阪など)
→ 未婚率が高い。理由は「仕事や趣味の選択肢が多い」「生活コストが高い」「自由な生き方を選ぶ人が多い」など。 - 地方(東北・北陸・九州など)
→ 都市部に比べて既婚率が高い。地域のつながりが強く、結婚や出産がライフイベントとして自然に受け入れられやすい。
総務省のデータ(引用)では、東京の生涯未婚率(50歳で未婚の人の割合)は男性で約32%、女性で約24%。一方で地方県では全国平均を下回る数字が多く、都市部ほど結婚しにくい環境 が浮き彫りになっています。
4. 男女別にみる「年収・学歴・地域差の影響」
男性
- 年収が結婚率に直結しやすい。
- 高学歴・大都市勤務=婚活市場で有利に働く。
- 地方在住でも安定した職業なら結婚率は高い。
女性
- 年収や学歴よりも「結婚意欲」が重要。
- 都市部女性は未婚率が高め。
- 地方女性は「結婚するのが当たり前」という意識がまだ残っている。
5. 婚活への実践的ヒント
データから分かるように、結婚率は 経済力・教育背景・地域環境 と密接に関係しています。
しかし、これらは「努力で変えられる部分」と「変えられない部分」があります。
- 年収 → 転職やスキルアップで上げる努力ができる
- 学歴 → 後から変えるのは難しいが、職業や実績で補える
- 地域 → 出会いの幅を広げるなら、オンライン婚活や結婚相談所を活用
つまり、自分が持つ条件に合った戦略を取ることが、結婚率を高めるカギになります。
まとめ(第4回)
- 男性は年収が高いほど結婚率が高い
- 学歴は男女で影響の仕方が違うが、今では高学歴女性も結婚率が高い
- 地域差は大きく、都市部は未婚率が高め、地方は結婚率が高め
- 婚活では「変えられる部分」を戦略的に工夫することが大切
次回(第5回・最終回)は、「結婚率から考える婚活戦略とフォリパートナーの成婚実績」 をまとめ、実際の婚活にどう役立てるかを解説します。
【第5回・最終回】結婚率から考える婚活戦略とフォリパートナーの成婚実績

1. 結婚率データが示す“婚活の現実”
これまでのデータを振り返ると、日本の結婚率には以下の特徴があります。
- 婚姻率は半世紀で半分以下に減少(1970年代の約10件→2023年は4件/人口1,000人あたり)
- 30代後半には多数が既婚(男性63%、女性73%)
- 年収・学歴・地域によって結婚率に差がある
- 都市部ほど未婚率が高く、地方の方が結婚しやすい
つまり、「結婚する人」と「結婚しない人」の二極化が進んでいるのです。
この現実を踏まえれば、婚活世代が取るべき戦略は明確です。
2. 結婚率を上げるための婚活戦略
結婚率は統計データですが、自分自身の行動によって「結婚できる側」に入ることは十分可能です。
戦略①:出会いの“母数”を増やす
データ上、結婚している人は「行動した人」です。自然な出会いが減少している今、結婚相談所や婚活イベント、オンラインサービスを活用して出会いの数を確保することが重要です。
戦略②:相手の条件を見極める
結婚率は年収・学歴・地域で差が出るため、「現実的に結婚を考えられる相手」を早めに見極めることが必要です。年収や仕事の安定性だけでなく、価値観や結婚観を丁寧に確認しましょう。
戦略③:ゴールを意識した交際をする
「いつまでに結婚するか」をお互いに明確にしないと、長い交際も結婚につながらないリスクがあります。特に30代以降は 交際から1年以内に結婚を決断するケース が増えています。
3. 男女別に考える婚活のポイント
男性向け
- 経済的な安定を示すことが結婚率を高める最大の要素。
- 年収に自信がなくても、誠実さや将来の計画を具体的に示すことでカバー可能。
女性向け
- 20代後半〜30代前半は結婚のチャンスが最も多い時期。
- 経済力や条件だけでなく「価値観の一致」を重視することで結婚率が高まる。
4. フォリパートナーの成婚実績
結婚相談所フォリパートナー(公式サイト)では、全国のIBJ加盟店ネットワークを活用し、累計2,000組以上の成婚をサポート。
特に注目すべきは 成婚率71%以上、男性成婚率94% という高い実績です。
これは「データを踏まえた戦略的な婚活支援」と「仲人によるきめ細やかなフォロー」があるからこそ実現できています。
実際に、30代後半男性が短期間で成婚に至ったケースや、地方と都市をつなぐ遠距離交際から結婚に結びついたケースも多数あります。
つまり、結婚率が低下している時代であっても、正しい環境とサポートがあれば十分に結婚できるのです。
5. まとめ(最終回)
- 日本の結婚率は減少しているが、多くの人はいずれ結婚している
- 年収・学歴・地域差などの要因が結婚率に影響
- 婚活では「出会いの母数」「条件の見極め」「ゴール意識」が重要
- 結婚相談所フォリパートナーは、データを活用したサポートで高い成婚率を実現
結婚は統計の数字ではなく、一人ひとりの行動の積み重ねで実現します。
「結婚率が低いから…」と悲観する必要はありません。むしろ、正しい戦略を取れば結婚できる確率は大きく上げられる のです。
👉 婚活で迷ったら、ぜひフォリパートナーに相談してみてください。
あなたの「結婚できる可能性」を最大限に引き出し、成婚への一歩を後押しします。
フォリパートナー編集部