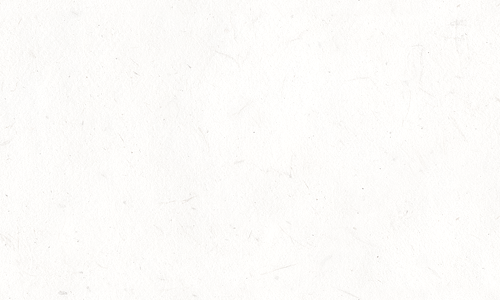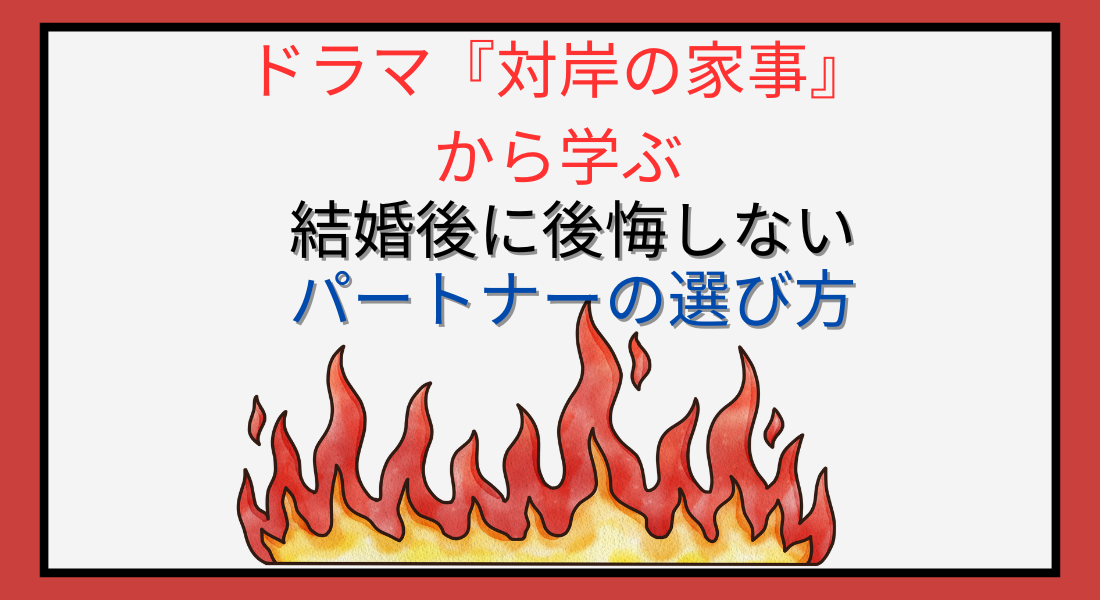
第1回:【対岸の火事!?】ドラマ『対岸の家事』が映し出す“家事・育児”のリアル

1. ドラマ『対岸の家事』とは?
近年、家庭や夫婦のあり方をテーマにしたドラマが増えていますが、その中でも話題を集めているのがドラマ『対岸の家事』です。
この作品は、専業主婦として日々家事や育児に奔走する主人公と、その対岸にいる「家事を他人事のように考えるパートナー」や社会の視線とのギャップを描いています。
タイトルにある「対岸」とは、まるで川の向こう岸から家事を眺めるだけで、当事者意識を持たない人々を象徴しています。
物語の中では、専業主婦の孤独感や、家事・育児を“見えない労働”として軽視する風潮、そして夫婦間での役割分担の不平等がリアルに描かれ、視聴者から多くの共感や議論を呼び起こしました。
2. 「対岸の家事」が突きつける問題
「対岸の家事」という言葉は、ドラマだけでなく、現実社会の夫婦関係や婚活においても大きな意味を持ちます。
婚活中の男女にとって、将来のパートナーが家事や育児を“自分事”として考えられるかどうかは、結婚生活の満足度を左右する重要なポイントです。
専業主婦であっても、家事や育児を一方的に背負うのは大きな負担ですし、共働き世帯ではなおさら、分担や協力が不可欠です。
しかし、現実には家事・育児を軽く見たり、「自分は外で稼いでいるから」という理由で関わりを避けるパートナーも少なくありません。
この“対岸”にいる意識は、結婚生活の中で摩擦や不満を生み出し、最悪の場合は関係破綻の原因にもなります。
3. 専業主婦・家事育児の価値を見直す
ドラマ『対岸の家事』は、専業主婦の立場から見た現実を描きつつ、その価値を問い直します。
内閣府の調査によると、家事・育児を金額換算した場合、その価値は年間数百万円から1,000万円以上になるという試算もあります(引用:内閣府 家事労働の評価に関する報告書)。
しかし、経済的な評価が数字として見えることは少なく、「やって当たり前」と思われがちです。
婚活中に「専業主婦を希望するか」「共働きを希望するか」という条件を話し合うとき、単に収入や生活費の話に終始するのではなく、家事や育児の価値をどう捉えているかまで確認しておくことが重要です。
4. 婚活で“対岸”を回避するための視点
婚活の場では、相手の性格や価値観を知ることがゴールではありません。
大事なのは、将来の結婚生活で「家事・育児を共に担えるか」という具体的なイメージを持つことです。
例えば、
- 相手が過去にどの程度家事をしてきたか
- 家事・育児についてどんな考えを持っているか
- 家族や親世代の家事分担の影響を受けていないか
こうした質問や観察によって、“対岸”に立ってしまう可能性のある相手かどうかを見極められます。
次回(第2回)では、ドラマ『対岸の家事』のエピソードから見える、夫婦間の価値観のズレとその背景について詳しく掘り下げ、婚活や結婚生活に活かせるポイントを解説します。
第2回:【対岸の火事!?】『対岸の家事』が描く夫婦間の価値観のズレと婚活への教訓

1. 印象的なエピソード①:見えない労働の軽視
ドラマ『対岸の家事』では、主人公が家事と育児で一日中動き回っても、夫からは「今日は何してたの?」と軽く聞かれる場面があります。
この短い一言に、家事や育児を「労働」として認めない意識が凝縮されています。
婚活中の方にとって、このエピソードは重要な示唆を与えます。
家事・育児は目に見える成果が数字や物品として残らないため、外部からは「楽そう」「暇そう」と誤解されやすいのです。
しかし、家族が快適に生活するための土台をつくる仕事であり、時間も体力も精神力も必要とします。
2. 印象的なエピソード②:パートナーの“他人事”な態度
別のシーンでは、主人公が発熱しても夫は「大丈夫?無理しないで」と言うだけで、家事や子どもの世話を自分から引き受けようとしません。
これは優しい言葉の裏に、「行動で支えよう」という当事者意識の欠如がある例です。
婚活の場で相手のこうした性質を見抜くのは難しいですが、デートや日常会話の中で
- 人の困りごとにどう対応してきたか
- 自分の役割を超えて動けるか
といった話題を引き出すことで、少しずつ本質が見えてきます。
3. 価値観のズレは“結婚後”に顕在化する
婚活では価値観の一致を重視すると言われますが、実は家事や育児に関する価値観は、結婚生活を始めてから鮮明になることが多いです。
理由は、独身時代には日常の中でそれらを共有する機会が少ないため。
特に専業主婦・共働きの選択や、家事分担の比率は、同棲や結婚生活に入って初めて本格的に直面します。
このため、婚活中の段階で意識的に「家庭内の役割」について話し合うことが重要です。
例えば、
- 料理・掃除・洗濯のどれが得意か
- 家事の外注(家事代行サービス)に対する考え方
- 子どもの夜泣きや病気の際の対応方針
などを具体的に聞いてみると、相手が“対岸”に立ってしまうタイプかどうかが見えてきます。
4. ドラマから学ぶ「婚活質問例」
『対岸の家事』を踏まえた婚活での実践的な質問例を挙げます。
- 「これまで家事をどのくらいしてきましたか?」
→経験値を知るだけでなく、家事をどう捉えているかが見える。 - 「もし結婚相手が体調を崩したらどうしますか?」
→行動力と責任感を見極める質問。 - 「休日の家事や育児はどう分担したいですか?」
→“自分事”として捉えているかを判断できる。
5. 婚活で「対岸」を避けるための心構え
結婚は「恋愛感情の延長」ではなく、「生活の共同経営」です。
その経営パートナーが、日常の運営に無関心では、やがて不満や摩擦が生じます。
婚活中から、恋愛面の相性だけでなく、家事・育児の価値を認め合える関係性を築ける相手を見極めることが大切です。
次回(第3回)では、専業主婦と共働き夫婦、それぞれにおける「対岸の家事」問題の現実と統計データを交えて解説し、婚活時の条件設定や相手選びの参考になる情報をお届けします。
第3回:【対岸の火事!?】専業主婦と共働き夫婦における「対岸の家事」問題の現実

1. 専業主婦世帯に潜む「対岸の家事」
専業主婦世帯では、「家事や育児は妻の仕事」という固定観念が根強く残っているケースが多く見られます。
総務省の「社会生活基本調査(2021年)」によれば、専業主婦世帯の夫の家事・育児時間は1日平均約1時間30分程度。これは共働き世帯の夫と比較しても大きな差はなく、むしろ「自分は働いていないから家事をすべて担うのが当然」と思い込んでしまう妻側の意識も、夫の“対岸化”を助長している場合があります。
この構造では、夫が「手伝う」という発想のまま固定化し、当事者として家事を分担する習慣が育ちません。
結果として、妻が体調を崩したときや急な用事が入ったときにも、夫は対応できず、生活が回らなくなるリスクが高まります。
ドラマ『対岸の家事』の中でも、主人公が病気で倒れた際、夫が家事の手順や子どもの世話の流れを全く把握しておらず、混乱するシーンが描かれています。
2. 共働き世帯でも残る「対岸」
共働き夫婦の場合、「仕事をしているのはお互い様」なのに、家事・育児の負担が偏るケースが多くあります。
厚生労働省の「令和4年 国民生活基礎調査」では、共働き世帯の妻は平日でも夫の約2〜3倍の家事・育児時間を費やしているという結果が出ています。
つまり、経済的な役割は対等でも、家庭内の役割は依然として不均衡なままです。
この背景には、
- 夫が「家事は苦手だから」と関与を避ける
- 妻が「自分の方が早く終わるから」と先回りして家事を担ってしまう
- 家事や育児のやり方について衝突を避けるため、話し合いを放置してしまう
といった要因があります。
婚活中に共働きを希望している場合でも、この「対岸の家事」リスクを軽視すると、結婚後に大きな摩擦が生じる可能性があります。
3. 統計から見る「家事分担の満足度」
内閣府の「男女共同参画白書(2023年版)」によると、夫婦間の家事分担に満足している割合は以下の通りです。
- 妻側の満足度:30%前後
- 夫側の満足度:60%以上
この差は、夫が“自分は十分やっている”と感じる一方で、妻は“まだ不十分”と感じていることを示しています。
婚活においても、この認識のギャップを埋められる相手かどうかは、長期的な関係性に直結します。
4. 婚活での条件設定に活かす
婚活時には、収入や住む場所などの条件だけでなく、家事・育児分担に関する条件を盛り込むことをおすすめします。
例えば、プロフィールや初期の会話で以下のような条件を共有することが有効です。
- 共働きの場合、平日・休日の家事分担割合はどのくらいを希望するか
- 家事代行やベビーシッターなど外部サービスの活用に前向きか
- 育児休暇の取得意欲があるかどうか
これらを明確にしておくことで、結婚後に「対岸の家事」状態になるリスクを減らせます。
5. データが示す婚活成功のヒント
婚活カウンセラーの現場感覚としても、家事や育児に前向きな男性は成婚率が高い傾向があります。
特に最近は、家事スキルを磨いたり、料理教室に通う男性も増えています。
これは単なるアピールではなく、生活能力の高さと当事者意識を示す行動であり、婚活市場では非常に評価されやすいのです。
次回(第4回)では、「対岸の家事」を防ぐために婚活中からできるパートナーシップ形成の6つのステップについて詳しく解説します。
ドラマのメッセージを踏まえつつ、実践的な婚活ノウハウに落とし込んでいきます。
第4回:【対岸の火事!?】「対岸の家事」を防ぐ!婚活中から始めるパートナーシップ形成6ステップ

ドラマ『対岸の家事』が描いたように、結婚後に相手が家事・育児を“自分事”として捉えられないと、日常生活の中で小さな不満が積み重なり、やがて関係の亀裂につながります。
これを避けるためには、婚活中から価値観や役割分担の意識を擦り合わせておくことが必要です。以下の6ステップは、結婚前からできる具体的なアプローチです。
ステップ1:家事・育児観の共有
行動例:お見合いやデートの会話で「家事や育児について、どういう分担が理想か?」を話す。
理由:結婚後の生活スタイルに関する価値観を早めに確認することで、「対岸の家事」状態を防ぎやすくなります。特に、専業主婦志向か共働き志向かによって分担の現実は大きく異なります。
ステップ2:過去の家事経験を聞く
行動例:「料理や掃除、洗濯で得意なものはありますか?」と軽く質問する。
理由:過去の家事経験は、結婚後の行動習慣につながります。まったく経験がない場合は、結婚前から少しずつ練習してもらえるかどうかが重要です。
ステップ3:具体的なシチュエーションでの対応を確認
行動例:「もし相手が体調を崩したら、家事や育児はどうしますか?」と尋ねる。
理由:優しい言葉だけでなく、行動でサポートできるかを見極める質問です。ドラマ『対岸の家事』でも、この場面の対応力が夫婦の信頼関係を左右していました。
ステップ4:休日の過ごし方をシミュレーション
行動例:「休日は家事と休息、どのくらいの割合にしますか?」という質問をしてみる。
理由:休日の家事参加度合いは、家事分担の実質的なバランスを示します。休日も“対岸”に立つタイプは、長期的に負担が偏る危険性があります。
ステップ5:外部サービスの活用意識を確認
行動例:「家事代行やベビーシッターは使ってもいいと思いますか?」と聞いてみる。
理由:共働き世帯や多忙な家庭では、外部サービスの利用が家事負担軽減に有効です。これに抵抗がある場合、家事育児負担が一方に集中するリスクが高まります。
ステップ6:感謝と承認の文化をつくる
行動例:交際中から、お互いの家事やサポートに対して「ありがとう」を口にする習慣を持つ。
理由:感謝の言葉は、家事育児を“当たり前”から“価値ある行動”へと位置づけます。小さな承認の積み重ねが、「対岸」への距離を縮めます。
婚活中に実践するメリット
これらのステップを婚活中に実践すると、単に条件やスペックで相手を選ぶのではなく、「結婚後も協力し合えるパートナー」を見極める力が養われます。
結果的に、結婚生活の満足度や持続性が高まり、離婚リスクも低減します。
ドラマが伝えた“見えない未来予測”
『対岸の家事』は、結婚生活の初期からのすれ違いが、何年も経った後に大きな不満や孤独感へとつながる過程を丁寧に描きました。
婚活中からこの教訓を活かすことは、将来のトラブル予防策そのものです。
次回(第5回・最終回)では、ドラマ『対岸の家事』から学ぶ、婚活成功のための総まとめと実践チェックリストをお届けします。
読み終わったその日から、結婚後の「対岸」をなくす行動をスタートできる内容にします。
第5回:【対岸の火事!?】『対岸の家事』から学ぶ婚活成功の総まとめ&実践チェックリスト

1. ドラマ『対岸の家事』が投げかけたメッセージ
ドラマ『対岸の家事』は、家事や育児を“自分事”として捉えられないパートナーとの生活が、どれほど日常に影響を与えるかをリアルに描き出しました。
それは専業主婦世帯でも共働き世帯でも変わらず、役割の偏りや理解不足は、小さな摩擦として積み重なり、やがて大きな不満や孤独感に変わります。
婚活中の段階でこうした危険信号を察知できれば、結婚後の“対岸”状態を回避しやすくなります。
では、どうすれば見抜けるのか?それを形にしたのが、以下の実践チェックリストです。
2. 「対岸の家事」を避けるための婚活チェックリスト
【価値観編】
- □ 家事や育児の価値について、相手が「労働」として認識している
- □ 専業主婦・共働きいずれの場合も、分担の必要性を理解している
- □ 家事・育児の経験をポジティブに語れる
【行動編】
- □ 相手が体調不良やトラブル時に、行動で助ける姿勢を見せられる
- □ 休日も家事・育児に参加する意欲がある
- □ 新しい家事スキルを学ぶことに前向き
【協力編】
- □ 家事代行やベビーシッターなど外部サービスに柔軟
- □ 家事や育児に関する話し合いを避けずにできる
- □ 相手の家事労働に対して感謝や労いの言葉をかけられる
3. 婚活中に意識すべき3つのポイント
- 価値観のすり合わせは早めに
結婚後ではなく、交際の初期段階から話し合うことで修正可能な部分が多くなります。 - 行動の一貫性を見極める
口では協力的でも、実際の行動が伴っていなければ「対岸」予備軍の可能性があります。 - 感謝を言葉にする習慣を持つ
日常の小さなサポートでも「ありがとう」を伝える関係は、分担意識を自然に育てます。
4. 婚活の現場から見える“成功のカギ”
結婚相談所のカウンセラー視点では、家事や育児に前向きな男性は成婚率が高く、結婚生活の満足度も高いという傾向があります。
理由は単純で、「相手の負担を減らそう」という意識が信頼や安心感を生み、関係を長く安定させるからです。
一方、婚活段階で家事や育児の話題を避ける男性は、結婚後に対岸化するケースが多く見られます。
これは男女問わず当てはまるため、女性側も「自分は全てやるつもり」という姿勢を見直すことが、良好な関係を築く第一歩です。
5. まとめ:婚活は“家事のチームメイト”探し
恋愛感情は結婚の大切な要素ですが、それだけでは長期的な関係は維持できません。
結婚生活は日々の積み重ねで成り立ち、その土台には家事や育児を共に担うパートナーシップがあります。
ドラマ『対岸の家事』は、そのパートナーシップの欠如がもたらす現実を、視覚的に教えてくれました。
婚活のゴールは“結婚すること”ではなく、“結婚生活を幸せに続けられる相手”を見つけること。
そのためには、相手が対岸からこちらへ渡ってきてくれる存在かどうか、見極める力が必要です。
フォリパートナー編集部